冒頭にあたって
被害者とそのご家族には心よりお悔やみ申し上げます。
本記事は事件の詳細を伝えるとともに、熊被害の現実を正しく理解し、今後の安全対策につなげるための情報提供を目的としています。
オホーツク・斜里町の羅臼岳でクマに襲われ亡くなった東京都墨田区の会社員・曽田圭亮さん(26)の死因が8月16日、「全身多発外傷による失血」であると警察が発表しました。
8月15日、曽田さんは遺体で見つかっていて、下半身に激しい損傷を負っていました。
引用元:https://www.fnn.jp/articles/-/917548?utm_source=chatgpt.com
北海道・羅臼岳で発生した熊事件では、登山者が襲われ遺体は下半身に激しい損傷を受けていました。
死因は大腿動脈などの破壊による失血死とみられ、人に慣れた熊による捕食型の襲撃が示唆されています。
専門家は「餌付けしないこと」が最も重要な予防策だと警告しています。
※このサイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天アソシエイト含む)を掲載しています。
事件の概要 ― 羅臼岳で熊に襲われた人
2025年8月、北海道斜里町の羅臼岳で痛ましい熊事件が発生しました。犠牲となったのは東京都在住の26歳男性登山者。友人と登山中にヒグマと遭遇し、突然襲撃を受けました。
友人は素手で抵抗しましたが圧倒的な力の差により男性は引きずられ、その後遺体で発見されています。
以下は羅臼町で撮影された、熊が自身より大きい獲物をハントする動画です。
熊は力が強く、人間が襲われたらひとたまりもありません。
【衝撃】北海道の羅臼町で熊が鹿をハント!
— 北海道の事件・事故速報 | 札幌発、ネットの力で嘘を暴く (@hokkaidowebnews) July 28, 2025
熊の出没情報が増えている中、羅臼では熊がかなり大きいサイズの鹿を襲う様子が目撃された。
サファリパークの3倍臨場感あるわ。#熊出没 #羅臼町pic.twitter.com/bY388ARuAS https://t.co/Gn585doNKz
警察と地元猟友会が駆除を行い、親子グマ3頭が撃たれました。現場の痕跡から、これらが加害個体だった可能性が高いと見られています。
とりわけ衝撃的だったのは、遺体が「下半身に激しい損傷」を受けていたことでした。
遺体の状況 ― 「下半身に激しい損傷」とは

「下半身に激しい損傷」とは
報道機関の記事にある「下半身に激しい損傷」とは、具体的にどのような被害を指すのでしょうか。
医学的な視点から推定されるのは、以下のような深刻な損傷です。
1. 大腿部の裂傷・噛み切り
ヒグマの顎の力は300~600kg以上とも言われ、大腿部の筋肉が噛み裂かれることで、 筋肉の欠損・骨の露出 に至るケースがあります。特に大腿動脈が噛み切られると、数分以内に致命的な出血を招きます。
2. 骨盤・腰部の破壊
腰回りは筋肉や靭帯が集中しており、強い噛みつきや引き裂き行動で 骨盤骨折や臓器損傷 が起こりえます。立ち上がる・逃げるといった行動が不可能になり、そのまま捕食対象となる危険性があります。
3. 内臓の露出・食害
骨盤内には膀胱・直腸・生殖器といった柔らかい臓器が集中しており、ここを損傷されると 内臓が露出する「食害型」の典型的な損傷 に至ります。三毛別羆事件や大雪山系での過去の事故でも、下半身や内臓が集中的に食われた事例が複数報告されています。
4. 顔面損傷との違い
一方で「排除型」の襲撃では顔面を潰されるケースもありますが、それは威嚇・無力化が目的であり、「捕食目的」の食害型とは異なる特徴です。
実際の死因は「全身多発外傷による失血死」とされています。
つまり、広範囲の軟部組織と血管が破壊され、きわめて短時間で生命活動が絶たれたと推定されます。
なぜ上半身より下半身を優先して損傷するのか?
報道では「下半身に激しい損傷」と表現されるケースが目立ちます。これは偶然ではなく、解剖学的な要因とヒグマの行動特性の両方が関わっています。
1. 解剖学的な要因
- 上半身は胸郭に守られている
心臓・肺・肝臓などの重要臓器は肋骨に囲まれており、外部からの噛みつきや引き裂きでは直接損傷を与えにくい構造になっています。 - 下半身は防御が薄い
大腿部や骨盤部は骨格による防御が弱く、筋肉や血管が露出しやすい位置にあります。特に大腿動脈や外腸骨動脈は噛み切られると数分以内に致命的な出血を招きます。 - 柔らかい臓器が集中
骨盤内には膀胱・直腸・生殖器などがあり、破壊されやすく「激しい損傷」として報じられる背景になります。
2. 行動学的な要因
- 逃走阻止のための下半身攻撃
熊は獲物を「動けなくする」ことを優先します。太ももや臀部を噛まれることで人は立てなくなり、短時間で制圧されます。 - 捕食効率の高さ
下半身の筋肉(大腿部・臀部)は肉量が豊富で柔らかく、捕食動物にとって食べやすい部位です。熊は理にかなった行動として、まず下半身から食害する傾向があります。
つまり、
- 胸部は強固に守られているため攻撃対象になりにくい
- 下半身は致命的損傷を与えやすく、かつ捕食効率が高い
この2点が重なり、ヒグマの襲撃では「下半身に激しい損傷」がよく見られるのです。
過去の熊事件との共通点 ― 羅臼岳事件の位置づけ

ヒグマによる人身事故は大きく分けて3つのパターンがあります。
- 人を食べる目的で襲う「食害」
- 外敵排除を目的とした「排除」
- 戯れや苛立ちによる「戯れ・苛立ち」
ヒグマによるヒトへの加害要因は、人を食べる目的で襲撃する「食害」、人が所持している食べ物などを入手する、ヒグマの所有物を人が所持している、猟師に対する反撃、不意に出会ったときの先制攻撃などで、人を排除するために襲う行為としての「排除」、人を戯れの対象とする、いら立っているなどで襲う「戯れ・苛立ち」の3つに大別されている。
引用元:高橋正弘「ヒグマによる人身事故から環境教育の課題を析出する試み」(2020年)
今回の羅臼岳での事件は、現場周辺で「人の残した食べ物やゴミを漁る熊」が以前から目撃されていたことから、人慣れによって人間=食料と認識した個体による、最初から「食害」目的の襲撃であった可能性が高いと推測されます。
ではここで、過去の熊事件をいくつか確認していきます。
福岡大ワンダーフォーゲル部事件(1970年)
大雪山系トムラウシ山で福岡大学山岳部員が襲撃され、3人が犠牲となりました。
当時の記録では、大腿動脈を噛み切られたことで数分以内に失血死した例が報告されています。
この事件は「登山史上最悪のヒグマ事故」とも呼ばれ、後に熊対策の研究が本格化する契機となりました。
この事件は当初、熊が外敵排除を目的に襲い、その後に食害へと移行したと考えられています。
👉 排除から食害への移行が特徴。1
三毛別羆事件(1915年)
北海道苫前村の三毛別集落で発生した、日本史上最悪とされる獣害事件。7人が死亡し、犠牲者は下半身や腹部を中心に食害されました。
特に臓器や大腿部の肉が集中的に奪われており、冬眠前のエネルギー補給として「高栄養部位」を選んでいたと推察されます。
👉 最初から食害目的で、人間を「獲物」として扱った典型例。
他の山岳地帯での遭難事故
日高山脈などの事例でも、顔面を潰されるケースがある一方で、腰部や大腿部を重点的に噛まれる例が複数報告されています。(顔面を潰されるのは「排除型」の攻撃)
効率よく致命傷を与えつつ、栄養価の高い下半身から摂食を開始する、という傾向が見られます。
羅臼岳事件との比較と考察
過去の事件と照らし合わせると、羅臼岳での事例は次のような特徴を持っています。
- 福岡大ワンダーフォーゲル部事件のように「排除→食害」ではなく、初動から食害目的だった可能性
- 三毛別事件のように「人間=獲物」と認識し、下半身から効率的に攻撃・食害した点で一致
- 人慣れが進んだ個体であったため、通常の山岳事故以上にリスクが高まっていた
つまり、羅臼岳事件は「人慣れによる食害型ヒグマ事故」として位置づけられ、従来の「排除型」事故とは一線を画す深刻さを持っています。
👉 歴史的な熊事件のパターンの延長線上にありながらも、「人慣れ」という現代特有のリスクが加わったことで発生した新たな類型と考えることができます。
食害型と排除型 ― ヒグマ事故の比較
| 特徴 | 食害型 | 排除型 |
|---|---|---|
| 攻撃の狙い | 初動から下半身(大腿・腰部)を狙う。大血管を噛み切り、効率的に致命傷を与える。 | 主に威嚇や一撃で排除を目的とする。致命傷にならない場合も多い。 |
| 人間の位置づけ | 「食料」「獲物」として認識。捕食行動に直結。 | 「邪魔者」として認識。縄張りや安全を守るための行動。 |
| 発生しやすい状況 | 人慣れした個体に多い。ゴミや餌付けで人間=食料と記憶している。 | 繁殖期や子連れ、猟師との遭遇、不意の接近などで起こりやすい。 |
| 襲撃後の行動 | 完全に動かなくなるまで執拗に攻撃し、捕食に移る。 | 一撃や短時間の攻撃後に退散するケースも多い。 |
| 危険度 | 致死率が極めて高い。人間を食料と認識した個体は繰り返し襲う可能性あり。 | 危険性は高いが、攻撃が短時間で終わる場合があり、食害型よりは低い。 |
熊の北海道における被害傾向

北海道全体ではヒグマの出没件数が年々増加しており、とくに知床半島や羅臼岳はヒグマ密度が非常に高い地域として知られています。観光客や登山者の増加に伴い、人間と熊との接触リスクはさらに拡大しています。
羅臼岳周辺では、以前から「人の残した食べ物やゴミをあさる熊」の目撃が相次いでいました。こうした行動を繰り返すうちに、熊は人間への警戒心を失い、「人に慣れた熊」へと変化していきます。人に慣れた熊は、従来の野生熊のように逃げず、逆に人間に近づいたり襲撃するリスクが高まるため、専門家も危険性を強調しています。
実際、北海道内の熊事件にはいくつかの共通点が見られます。
- 単独または少人数での登山
- 早朝・夕方など、熊の活動が活発な時間帯の行動
- 食料やゴミの管理不足
これらの条件が重なった場合、熊との遭遇率や襲撃リスクは大幅に上がります。
今回の羅臼岳での事件も、人慣れした熊が登山者に接近し、結果として大きな被害につながった可能性が高いと考えられます。
👉 熊被害を防ぐためには、出没情報の確認や登山計画の工夫はもちろん、「餌付けをしない」「食べ物やゴミを絶対に残さない」という基本的なルールの徹底が欠かせません。
登山者への警鐘 ― 熊被害を防ぐために
ヒグマ被害は決して過去の事件ではなく、現在進行形のリスクです。特に北海道・知床半島や羅臼岳のような「ヒグマ密度が非常に高い地域」では、登山者や観光客の行動次第で生死が分かれることもあります。以下の対策は必ず意識してください。
1. 熊鈴やラジオで存在を知らせる
熊は基本的に人間を避ける動物です。熊鈴やラジオで音を出すことは、最も手軽で有効な予防策のひとつです。ただし、近年は人間に慣れた熊の存在が指摘されており、その場合は鈴の音が逆に「食べ物の合図」と誤解されるリスクもあります。「鈴だけに頼らない」ことが重要です。
2. 食料やゴミを山に残さない
人慣れの最大要因は「食べ物」です。
ゴミや食料の管理を怠ると、熊は人間=食料と結びつけて記憶します。これが次の被害を呼び込む「負の連鎖」の出発点です。必ず持ち帰りを徹底してください。
また、最近は車から餌付けする行為も大きな問題となっています。観光地や林道で食べ物を与えられた熊は、人間に慣れ、やがて「人間=餌」と認識してしまいます。こうした熊は攻撃性が増し、駆除される運命をたどることが多いのです。
👉 ゴミや食料を残さないのはもちろん、安易な餌付け行為は“熊を殺す行為”にもつながることを強く認識してください。
3. 出没情報を確認する
北海道内では毎日のように熊の出没情報が公開されています。登山前には必ず自治体や道警、環境省などの発表をチェックし、危険が予測されるルートは避けましょう。
4. 複数人で行動する
単独登山は熊被害のリスクを著しく高めます。複数人で行動するだけで、襲撃のリスクは大幅に低下します。
5. 遭遇してしまった時に命を守る最後の砦 ― ベアスプレー
クマ鈴やラジオはあくまで「予防策」。
しかし、実際にヒグマと鉢合わせしてしまった瞬間、命を守れるのはただ一つ、ベアスプレーです。
米国やカナダでの研究によれば、ベアスプレーは92%の事例で熊の攻撃を止める効果が確認されており、使用者のほとんどが無傷で助かっています。これは銃器よりも高い成功率とされ、ヒグマ対策の「最終手段」として世界中のレンジャーやガイドに信頼されています。2
その中でも特に実績があるのが、
👉 「OUTBACK 熊撃退スプレー カウンターアソールト・ストロンガー(正規輸入品 CA290)」。
- 日本で30年以上の販売実績
- 北海道のプロガイドやレンジャーも愛用
- 信頼できる正規輸入品で安心
万一の時、ほんの数秒の判断が生死を分けます。
「持っていて助かった」という未来と、「持っていれば…」と悔やむ未来、あなたはどちらを選びますか?
⬇️ 北海道で登山・釣り・キャンプをする方に必須の装備はこちらら
Q&A(FAQ)

Q1. 北海道・羅臼岳で熊に襲われた遺体はどのような状態でしたか?
A1. 顔や上半身にも傷がありましたが、特に下半身に激しい損傷があり、大腿動脈の切断による失血死と推定されています。
Q2. なぜ熊に襲われた人は「下半身が激しく損傷」するのですか?
A2. 熊は捕食時に柔らかい腹部や太ももから食害を始める傾向があるためです。
Q3. 羅臼岳の熊事件と過去の事件に共通点はありますか?
A3. 福岡大ワンダーフォーゲル部事件や三毛別羆事件でも、犠牲者の下半身に激しい損傷が見られました。
Q4. 羅臼岳の熊は「人に慣れていた」とはどういう意味ですか?
A4. 人間の残した食べ物やゴミをあさり、警戒心を失った熊は人間を恐れなくなり、襲撃リスクが高まります。
Q5. 熊に襲われないために登山者ができる対策は?
A5. 熊鈴やラジオ、食料管理、最新ニュースの確認が基本です。実際に襲われた場合を想定し、熊スプレーを携帯しておきましょう。
Q6. 人に慣れた熊にクマ鈴は効果がありますか?
A6. 野生熊には有効ですが、人に慣れた熊には逆効果の可能性があります。状況に応じた判断が必要です。
まとめ ― 熊事件が示す現実と注意喚起
今回の事件は、捕食型の襲撃の可能性が高く、下半身の激しい損傷が致命的な失血死につながりました。
被害者とそのご家族には、改めて心よりお悔やみ申し上げます。
そして学ぶべき教訓は――
「熊に餌付けをしない」こと。
人間の食べ物に慣れた熊は警戒心を失い、結果的に人間も熊も不幸にします。
自然と共存するために、登山者や観光客ひとりひとりの責任ある行動が求められます。
最近の記事
- 【熊 下半身 激しく損傷】北海道羅臼岳で熊事件、遺体に見られた損傷とは
- プール活動時の熱中症予防と水温・気温の中止基準について【学校薬剤師:水質検査】
- プールで嘔吐した児童がいた場合の対応について【学校薬剤師:水質検査】
- “郷土の森公園”水遊びの池(じゃぶじゃぶ池)で思いっきり水遊び!駐車場情報もチェック
- アムロジピン服用中に避けるべき食べ物は?食べてはいけないものの完全ガイド
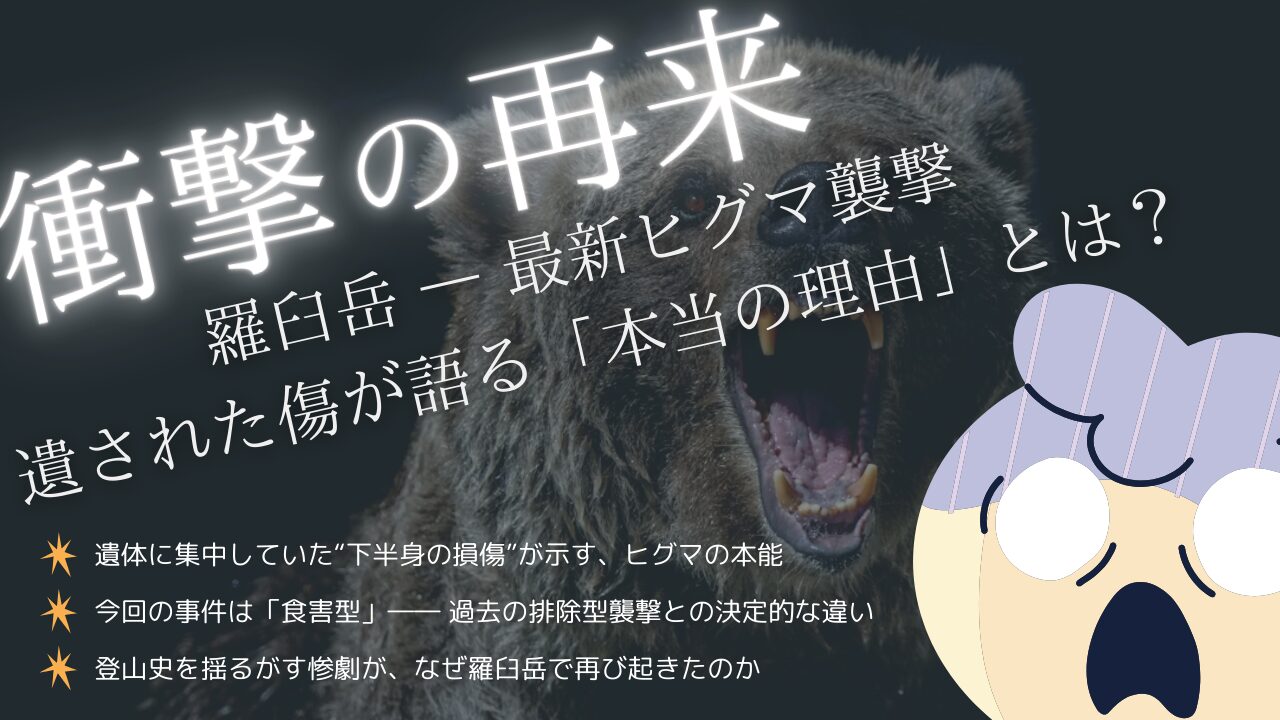

コメント